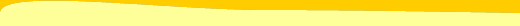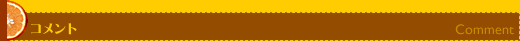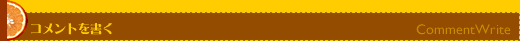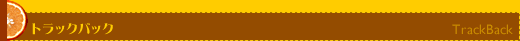水谷先生を知ったのは、先月ぐらいかな?
NHKで先生のドキュメンタリーを見た。
先生の生きざまに、心の底から涙と感動を貰いました。
こんな人が、いたなんて!!
■水谷先生著書
夜回り先生の卒業証書 冬来たりならば春遠からじ
ドラッグ世代 薬物汚染と闘う夜回り先生
さらば、哀しみの青春 伝えたい。闇に沈む子どもたちの哀しみを…
さよならが、いえなくて 助けて、哀しみから
夜回り先生
夜回り先生と夜眠れない子どもたち
■水谷先生インタビュー
横浜の定時制高校の教員となった13年前から、夜の授業終了後、繁華街を回る「夜回り先生」として有名な水谷修氏。街にいる子どもたちに声をかけ、悩みを聞き、薬物や暴力団との関わりなど彼らが抱える問題を一緒に解決してきた。定時制高校教員の友人の「夜間高校の腐った生徒にいい教育はできない」という言葉をきっかけに、有数の受験校から定時制高校へと転任、同時に夜回りを始めた。今年2月に『夜回り先生』を発刊。街にいる子どもたちに声をかけ続けることはもちろん、全国各地で講演を行い、またメールや電話での相談にも精力的に応じている。これまでに1万人以上の子どもたちと出会い、彼らを救ってきた水谷先生にお話をうかがった。
−−『夜回り先生』は25万部というベストセラーになりました。
「一冊目の本を出したきっかけは、2年前のある女子高生との出会いです。僕の講演を聞きに来た彼女は、リストカットの常習者でした。僕の専門は薬物乱用や少年非行、少年犯罪で、いわゆる“夜の闇に沈んだ子どもたち”をどう昼の世界に戻すかが課題でした。それまでリストカットという言葉は知っていましたが、見たこともかかわったこともなかった。だが彼女との出会いをきっかけに周囲を見渡してみると、リストカットしたり、オーバードーズ(OD・処方薬の過剰摂取など)、自殺願望を持つ子どもたちが非常に多くなっていることに気付き、これはまずいと思ったんです。
彼らに『苦しんでいるのはお前だけじゃないよ』と言うために、一冊目の本を出したんです。親や先生がお前はだめだと言っても、少なくとも水谷は『いいんだよ』と許すよ。でも『死にたい』だけはだめだよ。水谷がそばにいるから、ここへ集まっておいで。そういうメッセージです」
−−『夜回り先生』は2月、続編の『夜回り先生と夜眠れない子どもたち』は10月と、かなりハイスピードでの発刊ですね。
「今の社会は非常に攻撃的です。『いいんだよ』じゃない。『だめだよ』です。『何やってんだ』と上司は部下を叱責する。部下は家に帰って奥さんに当たる。奥さんは子どもに当たる。子どもは学校で『こんな問題もできないのか』と叱責される。世の中全体がイライラいらいらしている。そのすべてが子ども達に集約されている。
子どもたちと接していてわかったのは、非行・犯罪を繰り広げる子と、リストカットしたり、不登校になったりする子と、その根っこは一緒なんだということ。僕は彼らのことをまとめて、“夜眠れない子どもたち”と呼びました。僕がかかわってきた、ある意味で元気のある“夜の闇に沈んだ子どもたち”は、実は少数なんです。それよりはるかに多くの優しい子どもたちが、イライラした社会に圧迫され、攻撃的な社会につまはじきにされることで、自分を責め、心がぱんぱんになった結果、リストカットなどを繰り返している。
僕は“夜眠れない子どもたち”みんなに向けて、過去のことを認めた上で、『明日のことを水谷と一緒に考えよう』というメッセージを伝えたくて、2冊目の本を書きました」
−−今の社会は大人と子どもが隔絶している印象が強くあります。
「リストカットやODをする子は死にたいわけではなく、追いつめられた結果なんです。心の閉塞感に耐えられなくなって、やってしまう。でも助けがなければ、やがて本当に死んでしまいます。あるいは死なないまでも心が狂っていってしまう。大人たちだって、みんな実際は良い人たちなんです。でも優しさが出せない。だから僕は子どもたちと大人たちの掛け橋になりたい」
−−前著同様、今回も読みやすい作りになっていますね。
「この本では、明日へ進むために何をすればいいか、直接的には書いていません。原稿も原稿用紙190枚分ぐらいあったものを80枚ほどにまでそぎ落としています。文字はいらない。文字と文字の間に思いを込めていますから、子どもたちにはそこに景色を描いていってほしい。
これは読みやすくする意図ではなく、文字を減らすことで子どもたちに自分の頭で考えてほしいと考えた結果なのです」
−−「子どもは失敗して当たり前である。でもその失敗を許せない大人があまりにも多すぎる」という言葉が、強く印象に残りました。
「今の大人は失敗を許さないし、させないし、する前に助ける。学校を見てください。子どもに何をやらせていますか。学校はモノを考えられない子どもだらけにしている。失敗してもいいんです。なぜ、失敗したか、それを自分で考えることで、前に進むことができる。
自分でモノを考えさせるためには、しゃべっちゃだめなんです。待つことですよ。水谷、しゃべんないですよ。目の前で覚せい剤をやっている子がいても『やめろ』とは言いません。悲しい顔でただ座っているだけ。その子が『ごめんね』と言って初めて、その子が学んだわけでしょう。『やめろ、やめないと警察に訴えるぞ』『もうやりません』。こんなの教育じゃない。待てば子どもは学んでくれます」
−−この状況は変わらないのでしょうか。
「でも捨てたもんじゃありません。どこへ講演にいっても会場は満杯で、立ち見どころか床に座る人もいるぐらいです。昨日は熊本で講演をしてきたんですが、何の宣伝もしていないのに300人のホールで500人、集まってくれました。
大人たちからも、一冊目の本で『優しさを取り戻しました。いいんだよ、という気持ちを忘れてた。それに気付きました』という声がたくさん寄せられました。学校の教員からもたくさんいただきました。だからもっともっと講演に呼ばれたい。そして『いいんだよ』という言葉が世の中に広く浸透してくれればいいですね」
−−今までどれぐらいの子どもたちと出会われてきたのですか。
「一冊目が出たころは一万人ぐらいでしたか。今はそれをずいぶん超えましたね。メール相談は4万通以上です。講演は授業がない午前中や休みの日を使って日本中、北海道から九州、沖縄までどこへでも時間の許すかぎり行っています。7年間で1125回、約57万の人たちに子どもたちの悲しみを伝えてきました。夜回りも、横浜はもちろん、講演にいったさきざきでやっています。
休みはありません。休みがあれば誰かと会う。休んだら死にますよ、水谷は」
−−一緒に活動しようという教師はいないのですか。
「人にはそれぞれのやり方があります。これは僕のやり方。それに僕は一人でしか動かない。大人が二人になればそれは子どもにとって圧力です。子どもが待っているのは一人の大人です。一人の何の武器も持たない大人が、夜、街を回ってるから、子どもたちは心を開くのです。
ほかの人がどこか別の場所で似たような活動をすればいいということも、考えないですね。やりたい人はやればいい。僕の場合は、これまでに22人の生徒を救うことができずに死なせてしまった。それを償わなければならない。親が3名、子どもが19名。どの子も殺しちゃいけない子だった。やっぱりその子たちのことを考えたら償わなければいけないのです。償いのために、僕は僕の活動を続けるんです」
−−今回の本を含め、先生は亡くしてしまった子どものこと、救えなかった子どものことを正直に語り、それを悔いてらっしゃいますね。
「あんまり格好の良い先生じゃない。ミスばっかりですよ。殺した子だけじゃない。夜の闇に本当に沈んだ子だってたくさんいます。確かに助けた子の方が多いでしょう。9割以上は助けてるからそういう意味では日本の奇跡だと思う。それでも助けられなかった子たちはいて、その子たちに対する思いは強いですね」
−−この9月いっぱいで、体調やその他の理由から高校を退職されたとうかがいました。
「学校を辞めたので、“夜回り先生”じゃなくて“夜回りおじさん”になっちゃいました(笑)。なんだかサマにならなくてね。
僕は『リンパ腫』という病気で、もう長くはないんです。だから水谷は無謀な勝負に出てます。10月からはほぼ毎日、講演の予定を入れ、来年の3月までにあと本を2冊出す予定です。うまくいけば3冊出せるかもしれない。
原稿を書いていると、亡くした子どもたちを思い出すんです。そして自分のどこが間違っていたのかに気付く。気付くとまた、本腰を入れて夜回りにいけるんです」
−−特に治療を受けてらっしゃらないそうですが、治療を受けることで少しでも生徒のそばにいてあげようとはお考えにならないのですか。
「治療は受けません。生と死は人間が決めるもんじゃない。神が決めることであって、それを僕に求めるのは酷です。いれるだけはそばにいますよ。そこまでですね。だから死に方を気をつけないと。後追いがでますよ」
−−先生以外に信じられる大人に出会えなかった子どもたちには、その危険があるでしょうね。
「だから夜回りだけでなく、本や講演で大人たちに向かっても、メッセージを送ろうと思ったんです」
−−そこまで先生を駆り立てるものは何なのでしょうか。
「大人が相手にしてくれないからじゃないかな(笑)。子どもはちゃんと相手してくれるから。子どもが好きだから。やっぱり目の前で堕ちていく子どもを見ていられない。その子が幸せになれるなら、僕は必ず手助けをしてあげたいんです。
教員っていうのはね、生徒に心から先生と呼ばれて初めて先生になる。そのためには子どもの求めている夢になる。僕を作ったのは子どもですよ。子どものしてほしいことを真面目にしていくと、こうなるんです」
* * * * * * * *
子どもたちを守るためなら、暴力団と渡り合うことにも恐怖を感じることはない、という水谷先生。唯一怖いのは、「生徒を裏切ること。生徒に嫌われ、生徒からうそつきと言われるのが怖い」という。どこまでも生徒とともにあろうという姿勢。こんな大人に出会える子どもたちは、どんな逆境にいても、きっと幸福だ。
Yahoo!ブックスより転載
PR